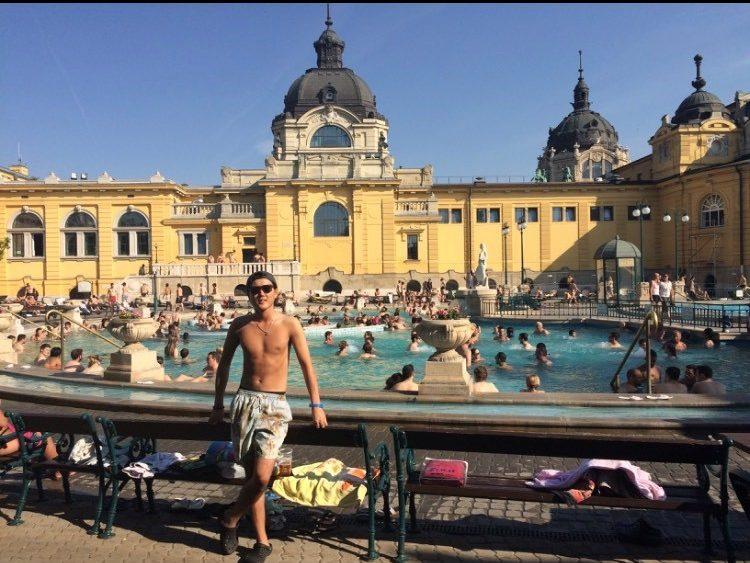【自己紹介】人とピザと時々地獄
第1章 独裁者が飼う鯨の傍らでロリポップを舐める
「ルーマニアっていいところなんですよ。
街は美しくて綺麗だし、人はあたたかくてやさしいし、おまけに美男美女であふれているし!
そして何より飯がうまくて物価が安い!
これ以上望むものはないって感じですね!!」
というようなありきたりなコメントはルーマニアの魅力を殺すことになるだろう。ルーマニアの光と影は単に「美しい」だとか「いい」だとかいう言葉では形容しがたいからだ。
筆者はルーマニアという国に二度しか訪れことがない。おそらく、一般的には “少ない” ほうだろう。滞在もそれぞれ二週間ほどだ。訪問前はルーマニアがどこにあるかさえわからなかった。唯一知っていたことはサッカーがなんとなく強い国だった “気がする” ということと、 Alexandra Stan という美女を生み出した国であるということだ。私の Alexandra のことについては後ほど書き連ねるとしよう。
そんなルーマニア初心者なわけだが、筆者なりにこの国の良さを見出せたのではないかと思う。国っていうのは、その土地に住む人々が築いた「文化」の集合体であるがゆえ、人間と同じで内面を見ずして良さは語れない。外側しか見ていないと独裁者チャウシェスクのようになってしまうかもしれない…。
ルーマニアの首都、ブカレストには “Palatul Parlamentului (通称:国民の館)” という巨大な建造物がある。正面から見ても後ろから見ても横から見てもただただぶっきら棒であり、我が物顔で立っている。
国民の館に入ると、まずは厳重なセキュリティが待ち構えている。そりゃ当然のことだ。国民の館はいわゆる日本でいう国会議事堂なのだから。当たり前だが警備の人は二コリともしない。多分ブカレストで一番真剣に仕事している人だろう。そのような真面目な警備には決まってボディを隈なく探られるわけだが、その試練を乗り越えれば、あとはガイドさんに連れられて国民の館様のおなかに入っていくわけだ。まるで鯨に飲み込まれたピノキオになった気分になるだろう。外から見たあの圧倒的な存在感はいわば視覚の暴力であり、中から見てもその太刀打ちのできなさに絶望感さえ覚える。しかしながら、ピノキオは鯨の口蓋垂に刺激を与え、吃逆を起こさせることで見事その体内から脱出できたわけだが、館様のかつては絢爛豪華で煌びやかに輝くシャンデリアであった口蓋垂には地面から人を縦に10個重ねたところで到底到達できない高さに位置しているがゆえ、おとなしく飲み込まれるほかないのである。私は己の小ささを自覚させられた。館様はいつも電車に乗れば周りの頭を見下ろしながら余裕をぶっこいている私に鉄槌を下したのだ。それでも上には上がいるから世の中面白い。館様さえ、米国のペンタゴンを目の前にしては抗うことさえできないわけだ。さすがはアベンジャーズの生みの国。強いですな。おそらく、日本でも時々出くわす巨大な仏像を見たことがある人にはこの絶望感のようなものを感じ取ってもらえるはずだ。巨像恐怖症の人は要注意である。
ここで、少し補足すると、国民の館はアメリカの国防総省ペンタゴンに次いで2番目に世界で大きな建物なんです。ほんとうに大きいので度肝を抜かれますよ。日テレの人気番組である『世界の果てまでイッテQ!』ではイモトアヤコさんが建物の前で記念撮影していたので、この記事を読んでくれている方の中にも知っている人はいるんじゃないでしょうか。中に入ると「すごいなぁ!」」と感動するはずです。かくいう私も、顎関節症を引き起こすんじゃないかってぐらいに口をあんぐり開けて、室内に居ながらにしてどこか遠くを眺め見入ってしまいました。多分周りの人たちに「日本人はとんでもなく間抜けな顔してるんだな」と思われていたに違いないでしょう。でも、不思議なんです。すごいだけで、美しいとか綺麗とか、そんな感情はわかないんですよね。信じられないくらいの建設費がかかっていますから、もちろん内部の装飾も一流品なのでしょうが、3,000室以上ある中で明かりがともされているのはほんのわずかです。仮に全部屋の電気をつけていたら億単位の電気代がかかってしまうとか。ですから、シャンデリアさえも鯨ののどちんこのようにただぶら下がっているって感じなんです。「空虚」という言葉がまさにぴったり当てはまるんじゃないでしょうか。この建物には心がない。チャウシェスクは権力欲しさのあまり、国民の内面は見れていなかったということなんですね。
先述したように、チャウシェスクは独裁者だったわけですが、「独裁者」と聞くとかつてチャールズ・チャップリンが痛烈に風刺したドイツの独裁者、アドルフ・ヒトラーを思い浮かべる人がほとんどでしょう。しかし、私の親の世代に聞けば、チャウシェスクを知る人も多いようです。1989年、東欧で広がった民主化運動の波にのまれたチャウシェスクとその妻は公開処刑され、その様子が世界各国に報道されたからです。私は歴史に疎いので、ここで彼についての詳細を語ることは控えますが、ルーマニア国民の経済状況も考えずに人口を増やす運動の一環として妊娠中絶を禁止する法律を作ったり、先に述べたルーマニアの負の遺産である『国民の館』を作ったりと、多大な影響を与えた人物であるわけですから、今現在のルーマニアを知りたい人にとっても必須の知識となるでしょう。また、チャウシェスク政権崩壊後は、上述したチャウシェスクの身勝手さにより生まれた “マンホール・チルドレン” が現れ、大きな社会問題となりました。この辺も押さえておくとよいでしょう。
さて、ここまでルーマニアのダークサイドを語ってきたわけだが、闇が深ければ深いほど光が際立つわけで、ここからはライトな一面について少し語ろうと思う。
ここでやっと私の Alexandra について語ることができる。読者のみなさんは “Mr. Saxobeat” という曲をご存知かな?世界的にヒットした彼女の代表曲である。彼女のあのナイスバディーには世の男性のみならず女性さえも鼻血ブーなわけだが、彼女の魅力はその声にある。Saxobeat で響き渡るサックスのクールな音色が彼女の持つ個性的なハスキーボイスとうまくマッチングしているのだ。ヨーロッパで流行っているダンスミュージックは私にはどうも同じように聞こえてしまうが、そこに新風を巻き起こしたのが彼女なのかもしれない。良曲なだけに今聞いても新しさを感じる。 そんな大ヒットを記録した “Mr. Saxobeat” は実は彼女のセカンドシングルである。せっかくの機会だからぜひファーストシングも聞いてあげて欲しい。いや、見てあげて欲しい、 “Lollipop (Param Pam Pam)” 。彼女は歌の冒頭で「アタシ、アメが好きなの。チョコレートも好きよ。アイスクリームもいいわね。でも、アタシのロリポップが一番好きなの…」と述べる。ロリポップってのは皆もよく知る渦巻き状のアメ、俗にいうペロペロキャンディーのことだ。「男の子たちも女の子たちもみんな好きなの。だって delicious なんだもん。 − 見て、感じて、触って、私の pam pam param pampam を。」この歌詞からは彼女が大の甘党であることと、ペロペロキャンディーのことが五感を使って味わうくらい好きであること、こんなかわいらしい歌詞を書けるくらい純粋無垢であることの3点がわかる。Mr. Saxobeat のような新しさはないものの非常に魅力的な曲だ。そして、魅力的な画だ。それなのになぜだろか。ここでその動画を紹介してはいけない気がする。なんとなく、理由はわからないが、このブログの持ち主である桑原氏の営業妨害にもなりそうだからやめておこう。
「ルーマニアのライトな一面を語りたいとか言っておいて、女の話かよ」と思った方、もう一度言いますが、私が最初に感じた魅力は彼女の声ですからね?あの声に魅了され、一目彼女に会いたいと思った。素敵な動機だと思いませんか?でも、悲しい哉、どこを探しても彼女はいませんでしたし、どういうわけか一生会えない気もします。ま、代わりに、彼女以上にとても素敵な人に出会うことができたのでとても満足なんですがね。
あっ、もう一つ、きっとルーマニアの音楽と聞いて「飲ま飲まイェイ」を思い浮かべた方もいらっしゃると思うのでここで言及しておきますが、「飲ま飲まイェイ」で有名な『恋のマイアヒ』を歌った O-ZONE はモルドバ出身のグループです。でも、モルドバの言葉ってルーマニア語に聞こえるんですよね。それもそのはず、モルドバ人の話す言語もルーマニア語だからなんです。ルーマニア語を公用語とする国は現在ルーマニアとモルドバだけ。もともとモルドバの公用語はモルドバ語でしたが、ルーマニア語と大差がないため、今は方言的な位置にあります。先ほど、 Alexandra の声に魅せられてルーマニアに行ったと述べましたが、実はルーマニアを最初の海外渡航先として選んだ最も大きな動機は「言語」でした。自分が知らない言語を話す人々がいる国に行ってみたかったのです。
序章 人とピザと時々地獄
2016年3月 作 (改)
生きて行く過程で立ちはだかる壁はいくつも存在するが、それらの壁を超越するような壁が現れたとき、その壁以外は壁でなくなる。人が多かれ少なかれ壁だと感じるものに、言葉の違いや文化の違い、人種の違いなどがあったりする。特に日本人においては、海外に行った際、それらの違いは明確化され、彼らの前に大きな壁として立ちはだかる。その影響で、長期に渡って海外に滞在する留学生なんかはホームシックになったりする。私が今回ルーマニアに滞在したのは2週間弱とかなり短い期間であったが、言葉や文化を壁と思うことはなかった。むしろ、そのようなことは「私が抱える問題」に比べると、随分と容易いものに今は思えてくる。
そもそも、私が今回ルーマニアを訪れるに至った理由だが、ある教授が『ルーマニアでバックパッカーをしよう』 というゼミを開講していたので、海外渡航経験のない私にとって非常に魅了的に思えたのだ。 長年英語を学習してきた者からすると、アメリカやイギリスなどの英語圏に行くことは夢であったりするが、私はまだ行きたくないのだ。英語は読めるし、会話もそれなりにできるからである。あとは、人を楽しませたり笑わせたりするような話術さえ磨けば、英語圏で困ることなどないだろう。それよりも、母語も英語も通じないような異国の地に行って、そこで直面する問題に自分がどう向き合えるかを試したかった。
我々がアンリコアンダ空港に降り立って、そこからブカレスト旧市街にあるホテルに向かうために、バスに乗らなければならなかった。バスのチケット売り場では英語は通じず、案内も全てルーマニア語であった。ここで、教授がルーマニア語で助けてくれたわけだが、もしこのときに先生がいなくても、私はなんとかバスのチケットを買ってバスで目的地に向かうことができたかもしれない。たとえルーマニア語を話せなくても、場所の名前さえわかれば、地図やジェスチャーで相手には伝わる。現地の言葉を聞き取ることなどできないわけだから、目的を達成するためには当然遠回りにはなるが、どこかへ行ったり、レストランで食べ物を注文して食べたり、スーパーで買い物したりできる。 仮にそこに長期滞在したとしても、何がどこにあって、どこで何が手に入るのかさえ把握しておけば生活するのに何一つ不自由しないだろう。
また、文化が違うということは、時に、人と人の間に対立を生む。例えば、ブカレストにあるコンビニで買い物をした際に、レジ打ちの女性の愛想があまりよくなかった。これをブカレストの女性は愛想が悪いと解釈すると、ただ単に反発するだけかもしれない。しかし、これを好意的に、ブカレストはルーマニアの首都であるから、当然人口も多いわけで、毎日多くの客の相手をしていると疲れるであろうと解釈することだってできる。このような些細なこともあれば、相手と意見が食い違ったり、上手く意思疎通できなかったりすることもあるだろうが、こういった対立は、固定観念を捨てたり、物事を多角的に見たりすることで回避できてしまう。要は、機転を利かせられるかどうかの問題だ。このように考えると文化や言葉など壁ではない。では、私にとっての壁は何なのか。全ては初めに述べた「私が抱える問題」である。
私は小さい頃から胃腸が弱くて、下痢という下痢に悩まされてきた。昨年の夏、ちょうどこの講義でルーマニアに行く計画を立てていた頃に、その原因がクローン病であることがわかった。しかし、クローン病による食事 制限は想像以上に厳しいものであった。このとき、私の生活は健常者の生活と比べると「異文化」になりつつあった。病気を診断される前からも、外を歩くときには常にトイレを気にしないといけず、何度か漏らしたことさえあった。これほどまでにひどい状態であったにもかかわらず、それでもルーマニアに行きたかった。私はルーマニアに着いてから自分の状態がどうなるかをある程度わかっていたが案の定であった。地下鉄や飛行機ですぐにトイレに行けなくて、なんとか自分で耐えつつも過呼吸寸前の状態になって苦しんだり、わざわざお金を払ってまで駅の便座のないトイレを使わなければいけなかったりであった。帰国する二日前には下血や下痢が出るようになり、薬の効き目が切れてきていることがわかった。旅の最中、先生や友人の助けもあったが、それでも最終的には一人で黙って自分と戦わなければならなかった。人間、本当に辛いときは言葉を発することさえできなくなるのだと改めて気づかされた。まさに、壁という壁の連続であり、時々、地獄が垣間見られた。それでも、苦しさ以上に楽しさと面白さがあった。
シギショアラからブラショフに向かうときに乗った電車は外観も車内も凄まじく印象に残っている。車体は “芸術的な” ペインティングに覆われ、見る側を圧倒した。車内での様子も面白い。我々が座っている後ろには十数人ほどのヤンキーがいて騒いでいる。ドアを開けて身を乗り出し何か叫んでいる者もいれば、ぷかぷかとタバコの煙を楽しんでいる者もいる。途中、駅がない場所で電車が停止し、切符を確認するおばちゃんが乗り込んできて、再び列車が発車する。おばちゃんはレスラー並みに体格が良いが愛想も素晴らしく良い。ニコリと微笑みながら我々の切符を切った。そして、おばちゃんはヤンキーの元へ行き、何やら盛んにディスカッションをしている。何を話していたかは当然わからないが、ヤンキーの盛り上がりが少し落ち着いたことから会話の内容を推測できた。そのあとおばちゃんはもう一人のヤク中っぽい顔の同僚が座っている席の横に座り、ポケットの中から取り出した真っ赤なリンゴに満面の笑みでかぶり付いた。私はその列車に乗りながら、まるで遡って別の時代にいるような気がした。そんな光景がなんだか面白く思え、私の気持ちを癒した。ブカレスト旧市街の街並み、ブラショフの黒の教会、トゥルダの岩塩鉱など様々な場所を訪れたが、結局、私の一番の思い出は、そういったルーマニアの人々が作り出す微笑ましくも温かい雰囲気である。食事制限を無視してまで旅の最後で頬張ったピザは最高であった。私はこうして壁を乗り越えたのだから、また行けるという希望を持つことにする…。
第2章 GOEN
実は序章には続きがある。第1章の冒頭で述べた通り、筆者はルーマニアに二度訪れている。一度目は2016年の2月。二度目は2018年の5月。序章の続きとはその間に起きた出来事である。簡単に説明すると、筆者が大学の資金 (とクラウドファンディングで得た少しの資金) を運用してルーマニアの学生を北海道に呼んだのだ。たったの二回だけだけど。ヨーロッパの中でもルーマニアの物価が東南アジア諸国並みであることから想像できると思うが、ルーマニアの学生にとって日本に来ることは決して容易いことではない。それでも日本に関心がある人は多くいる。私はそんな学生にももっとチャンスがあるべきだと思った。自分だってルーマニアに行けたのだから。実は一度目の帰国日に、向こうから札幌へ来る予定だった学生が一人いた。彼は某大学のエッセイコンテストで入賞し、札幌に5日間滞在する賞を与えられていた。しかし、自身の持つ肺の病気で当日ドタキャンしてしまった。空港のセキュリティコントロールも通って搭乗までもうすぐだった。彼とは定期的に連絡を取り合っているが、あの時本当は日本に来たかったらしい。私がプロジェクトを立ち上げた動機の一つは彼でもあったが、彼が再び挑戦することはなかった。でも、希望はまだあるから頑張り続けて欲しい。二度目もプロジェクトを行うに至った経緯には…と話すと長くなるので、ここでやめておく。関心がある方は私を見つけ手からお声掛けください。世界は広いようで狭いですから、案外、どこかでばったり遭遇するものです (笑)
これらのプロジェクトによって最終的に筆者の大学とルーマニアのある大学の間で協定を締結させることができた。これは筆者にとって非常に嬉しいことだった。しかし、その続きがない。協定はあっても実質的に機能していないからだ。だからせっかく結んだ協定を置いてけぼりにしている気がする。本来、ここで筆者は責任を感じる必要はない。二度のプロジェクトを通して、何人かのルーマニアの学生が抱いていた日本に行きたいという夢を現実にしたのだから。それでも筆者はなぜそんな気がしてしまうかというと、それは責任とかそんなものではなく、「好き」だからだ。そして、一種の使命感のようなものがあるからだ。
昨年の2月頃だったか。ガーナに学校を作って現地の子供たちの支援をしている堀田哲也さんという人に会った。堀田さんはずっとパチンコ屋で働いていたみたいだが、ある時、青年海外協力隊に応募し、ガーナに派遣されることになった。堀田さんは JICA が定めた2年という派遣期間で立派に任務を遂行した。2年が経った頃、JICA からその後の支援は全て自費になることを伝えられたが、それでも堀田さんは今でも支援を続けている。そこで辞めてしまっては後を引き継ぐ者がいないし、そもそも世界で支援を必要としている人は山ほどいて JICA はそれらの地域に人員を派遣しているからだという。そして、一度学校を建設してもそれを維持できる人がいないのも大きな理由の一つだ。堀田さんはよく人に「すごい」と言われたり思われたりするがそんなことないと言う。そして、「どうしてそんなことできるのか」、「なんでガーナなの?」と問われることが多々あると言うが、返す言葉は決まって「好きだから」であると言う。人を助けたいとかそういうことではなく「好きだから俺はやっているんだ」である。この言葉は筆者の胸に響いた。
話を戻すと、筆者は好きだからルーマニアに行ったり、学生を呼ぶプロジェクトをしたりしたわけだ。そして今後も続けるだろう。いつできるかわからないけど、何年も経ってからリブートされる映画のように、全く新しい形でもいいから続けたい。そして、筆者には好きでやっている支援がもう一つある。興味がある方は “World Youth Japan” とググってください。アメリカの中学生や高校生に日本の文化を体験してもらうプログラムのコーディネートを主な活動としてしている NPO で、石川園代っていう元プロスキーヤーで今は大学で講師もしているおばちゃんが理事長を務めている。つまり、私のボスだ。イギリスの諜報機関 MI6 で例えると、ボスが M で、私がジェームズ・ボンド。でも、我々は人を “殺める” 代わりに、人に “謝る”。思春期の子供たちは激しいですから。何をしでかすかわかりゃしない。もしこの活動に興味があればぜひ組織に一通メールをください。
私は今、大学院を卒業したばかりで、複数の仕事を掛け持ちしながら生活をしている。その一つがゲストハウスでの夜勤だ。月に二度ほど、週末の午後10:30から午前7:30まで、レセプションの番兵をしている。ここで仕事を始めてから1ヶ月半くらいが経過しようとしていたとき、変わったお客さんに出会った。どうやら、ヨーロッパの大学へ学生を送る事業をしているらしい。そのお客さんはここに来てから数ヶ月経つが、よほど居心地が良いらしい。こんな面白い人に会えるなんて私は本当に運が良い。おかげさまで私もここを離れられないでいる。桑原さんって人なんだけど…。
編集後記
こんな長いのに読んでくれてありがとう。これを見てルーマニアに行きたくなるだろうとは思えないが、少しでも関心を持ってくれたならば本当に嬉しい限りです。観光でも留学でもしたい人は『地球の歩き方』を買って読んでださい。もちろん国民の館のことも書いてありますよ。
いつかどこかでお会いしましょう。
La revedere!!
Suguru
P.S. 留学経験が一切ない私の記事を載せていただきありがとうございます。このブログの所有者さんが今後ルーマニアにも進出してくれることを切に願います (笑)